吉田たかよし院長のおすすめ記事

この効果を応用し、受験生も服装が脳に与える効果を利用すれば、勉強の集中力が上がったり、試験を受けているときに頭の働きがよくなり、志望校に合格するのに役立ちます。
イギリスで行われた研究の結果、「人間の脳は服装に支配されている・・・」という論文が発表されました、
警察官の服装をすると、正義感が強くなる・・・。
看護師の服装をすると、病人のケアを献身的に行いたくなる・・・。
それぞれ、服装が人間の脳の性質を変えているため、こういう現象が起きるのです。
この法則に従えば、受験生の場合も、「入試に受かる服装」をすれば、現実にも入試に受かりやすい脳に変わるということです。
これは、脳の前頭前野と大脳辺縁系のバランスによって決まります。
具体的には、どんな服装が、勉強しているときの集中力やヤル気を高めるのか?
試験を受けているときは、どのような服装だと、点数がアップするのか?
服装によって、脳はどのような変化をするのか?
どのようなことを実践したら、その効果をさらに倍増させられるのか?
受験生はもちろん、受験生の親御様も、これを知っておくと、受験が有利になります。
受験生を専門に診療する心療内科医として、今日から実践できる服装を利用した合格術を解説します!
実は、「脳の働きは服装に支配される」という論文が発表されているんです。
この現象を利用すれば、勉強をしているときや試験を受けるとき、服装をちょっとだけ工夫することで、脳が活発に情報処理を行なうように切り替えることができるのです。
また、試験を受ける直前の時間に、簡単なあることをするだけで、さらにこの効果が高まり、「受かる脳」に変わってくれる効果もあります。
これによって、ライバルに差をつけちゃいましょう!
「脳の働きは服装に支配される」というのは、どういうことか?
イギリスで行われた研究によって、志望校への合格を勝ち取るためにもも役立つ、とても興味深い脳の性質が解き明かされました。
私たちの脳は、常に自分がどんな服装をしているのかをモニターしているのです。
そして、無意識のうちに、その服装に合致した脳の働き方に調節しているということが解明されたのです。
脳にこうした性質があることを証明するために、いろんな実験が行われているのですが、たとえば、スーパーマンの服装をしたら本当にスーパマンに近い脳の働きになるという論文も出ているんです。
実験データを分析すると、この効果は、意欲や気力を高める効果が特に大きく、脳の働きを変える作用が強くて驚かされます。
この法則は、受験にも応用できます。
脳が「これは、勉強する服装だ!」と認識する服装を選んで着用したら、脳は「勉強する脳」に性質を変えるということです。
具体的に言うと、「勉強することに対してヤル気が高まり、集中力も持続しやすい脳になる」という効果が現れるわけです。
また、「これは、入試に受かる服装だ!」と認識する服装を選んで着用したら、脳は「入試に受かる脳」に性質を変えるわけです。
こちらは具体的に言うと、「気力が満ち溢れて、たくさんの問題をバリバリ解き続ける脳になる」ということです。
では、脳には、どうしてこのような効果が出るのでしょうか?
人間の脳にとって、複雑な社会の中で生きることは、とても大変なことです。
社会における自分の立場に合わせた立ち居振る舞いをするというのは、情報処理をしなければならないデータ量が膨大です。
これをすべて脳が情報処理を行い続けるのは、そのままだとかなり難しいことなのです。
思考力を生み出す脳の前頭前野の機能だけに頼って、社会的な立場にふさわしい言動とはどんなものか、すべて頭で考えるということだけをしていたら、現実の生活では追っつかないわけです。
そこで、人間の脳は、いちいち論理的思考力で考えるのをやめて、直感によって次の行動を実行するという方法を採用しました。
直感による行動は、脳の大脳辺縁系などが生み出す機能です。
この機能は大雑把なので間違えることもありますが、直感で行動すると、脳の負担が軽く、さらにはるかに早く行動できるというメリットがあります。
無意識のうちに服装に合わせた脳の働きに調節するというのも、こうした直感を利用した脳の戦略の一つなのです。
では、試験を受ける場合、着ていくと点数を上積みできる「受かる服装」とは、具体的には、どのようなものなのでしょうか?
服装は脳に対して情報を発信しています。
スーパーマンの服装は、悪を懲らしめるヒーローという社会的情報を発信しているから、スーパーマンの服装をすると、正義感や勇気が湧くというデータが実験で得られたわけです。
パイロットの服装だと、ミスをしなくなる・・・。
ナースの服装だと、献身的に患者のケアができる・・・。
理由は、まったく同じで、服装がそういう社会的情報を脳に発信しているからです。
受験生の場合は、試験で良い成績を取れるという社会的情報を自分自身の脳に発信してくれる服装にすれば、今、受けている目の前の試験についても、点数を上積みしてくれる脳の働きに切り替わるわけです。
そのためには、どんな服装がよいのか?
おすすめは、今までに受けたテストで、すごく良い成績が取れたときと同じ服装を選ぶということです。
はっきりと思い出せない場合でも、「多分これだった!」と思った服を着ていけばいいわけです。
本当は違う服だったとしても、心配はありません。
「服装で脳が変わる」というのは、自分の脳が作り出す作用です。
仮にそれが事実ではなくても、自分が「受かる服装」と思っていれば、それだけで気力が高まって「受かる脳」に変化してくれるわけです。
一方、普段、ご自宅で勉強するときに、やる気や集中力を高めるには、どんな服装がいいでしょうか?
おすすめは、制服など、学着ていくいく制服です。
脳の中では、毎日、「この服装をしているときは授業を受けて勉強する」という恒等式が成り立っています。
だから、自宅で勉強するときも、授業中と同じ服装をするのがよいわけです。
一方、勉強が終わったら、自宅でくつろげる服装に、速攻で変えるべきです。
そうしないと、「制服も自宅でくつろぐ服だ」という恒等式に脳内が塗り替えられてしまいます。
こうして、勉強するときは勉強の服装、くつろぐときはくつろぐ服装…といった具合に、服装でもメリハリをつけると、脳も勉強と休憩のメリハリをしっかりつけてくれます。
模擬テストで良い点数をとれたのは違う季節だった・・・という受験生も大丈夫です。
この効果は、身につければ発揮できるものなので、服ではなくても、靴下でも、髪留めでも、何でもいいんです。
とにかく、今まで受けたテストでバリバリ問題が解けた記憶と結びついているものを、何か一つでいいので身につけて、試験の会場に乗り込みましょう。
さらに、試験が始まる直前に、服でも靴下でも髪留めでも、その部分を触りながら、バリバリ問題が解けた経験を思い出しておきましょう。
それから本試験の問題に取りかかれば、気力が高まって「受かる脳」に切り替える効果はさらに高まります。
このように、服装の力を味方に付けて、気力を高めて合格を勝ち取っていただきたいのですが、残念ながら、脳の機能上の問題があって無気力になっている場合は、服装だけでは解決しません。
学力があるにも関わらず入試に落ちてしまう要因として「受験無気力症候群」はとても多く、その場合は、早急に対策が必要です。
以下の「受験無気力症候群」の説明も、ぜひ、ご一読ください。
本日、内容をアップデートして更新したばかりの解説記事です。
✓「受験無気力症候群・セルフチェック」を掲載しています!
勉強を続ける気力がなくなってきた受験生は、こちらで簡単に自己診断ができます。
✓ コロナ禍の影響で「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」が急増しています。これが、本来は学力があるはずなのに入試に落ちてしまう重大な要因になっています!
✓ 勉強のヤル気が急に出なくなった場合は、単なるサボリではなく、脳の前帯状回(Anterior cingulate cortex)など、何らかの脳の働きに起因する場合が多いので注意が必要です!
✓ 勉強はできないのに、ゲームやスマホなら熱心に取り組めるというのが、受験無気力症候群の最近の特徴です!
✓ ご自宅で誰でも簡単に実践できる「受験無気力症候群(Exam Apathy Syndrome)」の予防法をご紹介しています。
✓ 受験に特化した「光トポグラフィー検査」のデータを、最新の脳科学の研究成果を元に分析することで、最短の時間で受験無気力症候群から脱却し、志望校に合格できる脳に変えることができます!
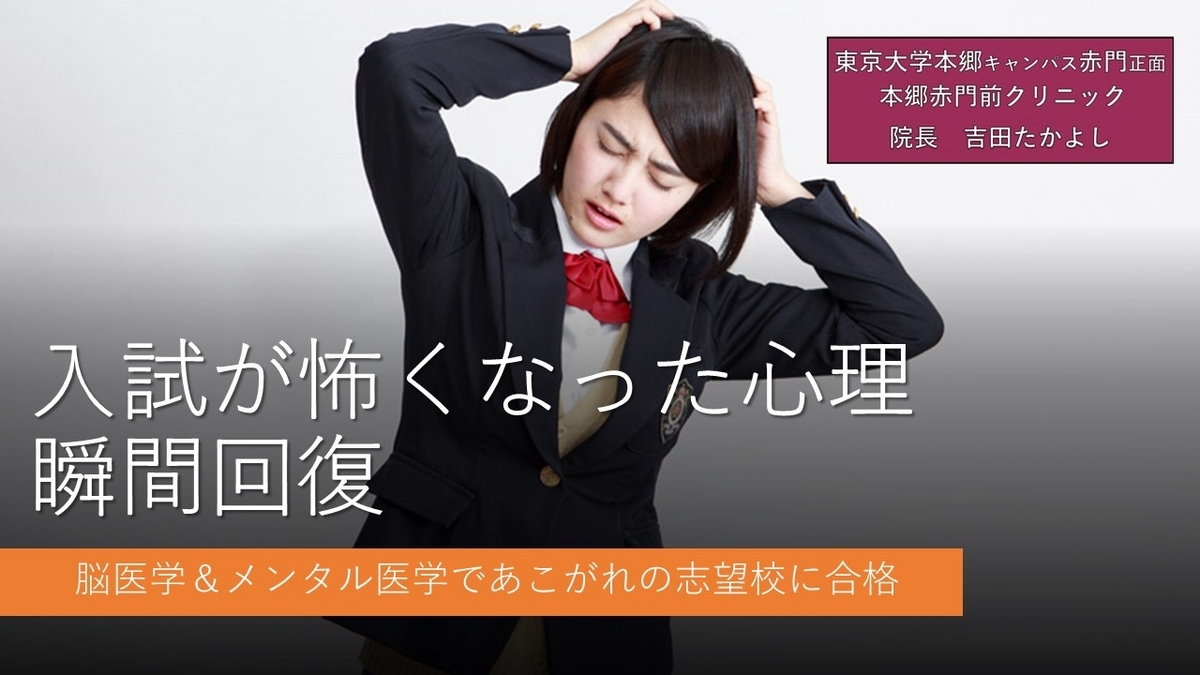
ただし、このような神経生理学的な方法で改善するのは、脳がシステムとして健康に機能している場合のみです。
それを超えてメンタルが不安定になっている受験生は、合格を勝ち取るためには、専門の脳医学に基づく治療が必要です。
ぜひ、以下の「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」についての記事もお読みください。
✓ 受験勉強の集中力・記憶力・ヤル気の低下は、受験うつや受験ストレスによる脳機能の不調によって生じる場合が多いのが特徴です。
✓ 「頑張ればなんとかなる」といった精神論で解決しようとすると、脳のストレスや疲労が悪化して逆効果となります。
✓ 受験に特化した専門の「磁気刺激治療」は、脳機能の不調を根本的に治療することにより、受験うつや受験ストレスに起因する障害を取り除き、志望校への合格に必要な集中力・記憶力・ヤル気の回復を図ります。
✓ 脳機能に合致した勉強方法への改善など「受験に特化したCBT治療」を組み合わせることにより、磁気刺激治療の効果を志望校へに合格に直結させられます!
✓ 光トポグラフィー検査による脳の活動データを元に、必要に応じて以下の5つの特別診療も併用します!
✓ メンタル医学と脳医学を総動員した以上の診療プログラムによって、あこがれの志望校への合格を実現しましょう!
「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」とは、2013年に全国で始めて、本郷赤門前クリニックが受験生に特化した特別診療プログラムとして開設したものです。
磁気刺激治療は、当時、アメリカではすでに画期的な治療法として普及しつつありましたが、日本ではほとんど行われておらず、医師ですら名前も知らないという人が多数派でした。
そのような時期に、いち早く画期的な治療成果に着目し、さらに、受験生のうつ症状にはとりわけ有効だということを発見し、受験生専門の治療プログラムに取り入れたのが「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」です。
突然、記憶力が低下した・・・。
勉強のヤル気がわいてこなくなった・・・。
イライラして勉強が進まない・・・。
優しかった子どもが急に暴言を吐くようになった・・・。
受験生にこのような異変が現れた場合、多くの親御様は、
「たるんでいる!」
「もっと気合を入れて頑張れ!」
「根性が足りないんだ!」
などと、精神論で解決しようとする方が少なくありません。
しかし、多くの場合、受験うつなど「受験脳機能障害」により、脳の働きが悪化していることが根本的な原因です。
そのため、精神論を振りかざして無理やり頑張らそうとすると、症状が悪化して効果になってしまう危険性が高いのです。

志望校への合格を勝ち取るためには、受験の当日まで、脳と心コンディションを良好な状態に保つ必要があります。
特に、受験勉強による脳疲労や入試に失敗するかもしれない精神的ストレスが、人体が乗り越えられる限界値であるストレス耐性を超えると、脳内の前頭前野の機能が劇的に低下します。
その結果、問題を粘り強く解くことができなくなるわけです。
受験生自身も受験生の親御様も、そうした事態を回避するため、その前の段階でストレスの状態をしっかりチェックしておき、適切な対策をとっていただきたいです。
今日、ご紹介するのは、そのためにとても役立つ声のチェックの方法のご紹介です。
3つのチェックポイントに着目すると、受験ストレスによって、脳にどれくらいダメージを受けているのか、ある程度は把握できるのです。
受験ストレスや「受験うつ」による脳機能の低下は、受験に失敗してしまう大きな要因です。
声のチェックは時間がかからず、とても簡単に実践できます。
だから、SOSサインを読み取ることは、受験にとって、とても大きなメリットがあります。
受験生ご本人はもちろん、ご家族も声を通して受験生の脳の状態をチェックしていただきたいのです。
声と受験ストレスは、具体的には、どのような関係があるのか?
受験ストレスに関する3つの声のチェックポイントとは、それぞれ、どのようなことなのか?
日々、受験生の脳と心を専門に診療している心療内科医としての経験と専門知識を元に、わかりやすく説明します。

実際、心療内科クリニックで問診をするとき、実は医者は、受け答えの内容だけでなく、声自体もチェックして、診断に役立てているんです。
音読の声をセルフチェックすれば、これと同じことが、ご自分でもご家族でもできるということです。
この前の模擬テストが思ったほどは点数が出なかった・・・。
じっくり考えないとできない応用問題が、最近、ちっとも解けない・・・。
覚えても覚えても、すぐ忘れてしまう・・・。
そのような自覚症状がある人は、まず、教科書でも参考書でもいいいので声に出して読んでみる、つまり音読をしてご自分の声をチェックしてみてください。
また、受験生の親御様は、食事の時などに、何気ない会話を通して、お子様の声をチェックしてあげてください。
ストレスを見極めるチェックポイントをわかりやすくご紹介しておきますので、どなたでも、簡単に実践できます。
まず、チェックしていただきたいのが声の高さです。
脳がストレスを溜め込むと、喉にある喉頭周囲筋群が収縮するため、声が高く、さらに声の高さがゆらぎを持つ傾向があるのです。
本来の自分の声より、なんだか不自然で、高く上ずったような、音楽で言ったらちょっとビブラートがかかったような、そんな声になっていたら要注意だということです。
それから、声が安定的に出ているかも、とても大事なチェックポイントです。
声を出すとき、脳は、腹筋や胸の筋肉と声帯の閉じ具合とを上手にバランスをとって、一定の流量速度で空気の流れができるように息を吐いています。
でも、受験ストレスや「受験うつ」による脳機能の低下が起こっていると、こうしたコントロールが精度の低下を起こすため、安定的な声は出せなくなるのです。
その結果、時折、声の強さが不自然に強くなったり、逆に、声が弱くなって、かすれたリ、とぎれとぎれになったりします。
また、喉にこもったような声になってしまうこともあります。
また、滑舌が悪くなっている場合も要注意です。
解剖学的には舌は筋肉のかたまりです。
これに加え、口の周囲の筋肉なども含め、発音に使う筋肉の全てを連動させて正確に動かさないと、正しい発音にはなりません。
こうした筋肉の連動した動きをコントロールしているのも脳なので、脳機能の不調は、そっくりそのまま、滑舌の悪化として表面化するわけです。
もともと滑舌が悪い人は気にしなくてもいいですが、以前の自分と比べて滑舌が悪くなったと感じたら、それは舌や口ではなく、脳の問題だと認識してください。
この他、声が極端に小さい、とぎれとぎれになる、読み間違いが多い・・・なども、受験ストレスや「受験うつ」による脳機能の低下で生じます。
ぜひ、今すぐセルフチェックをして、脳に起こっている異変を見逃さないようにしてください。
もし、音読をして、なにか脳のSOSサインが出ていたら、それは受験生にとって朗報かもしれません。
現在の成績は、あなたの実力ではなく、脳機能の低下で、見かけ上、下がっているだけなのかもしれないからです。
その場合は、逆に言えば、脳機能を直せば大幅に成績が上がるということを意味しているわけです。
根本的に学力が劣っているより、はるかに明るい未来が見えてきます。
該当する症状が見つかった方は、ぜひ、こちらの検査を受けてください。
【このページの要点】
①最新の光トポグラフィー検査(Optical Topography)で、勉強中の脳機能を科学的に分析します!!
②安全な近赤外光(near infrared radiation)で大脳新皮質の血流変化を測定するので、まったく安全です!
③大うつ病性障害(MDD)・双極性障害(BP)・統合失調症(SZ)などの誤診を防ぐこともできます!
④勉強のヤル気がわかない、集中力が持続しない、記憶できないなど、脳が抱える問題点が明確になります!
受験ストレスの状態を脳のレベルで科学的に診断するため、決定的に重要だといえるのが「光トポグラフィー検査(Optical Topography)」です。
そこで弊院では、早期合格コースの受験生の方に、真っ先にこの検査を受けていただいています。
「光トポグラフィー検査」を行うと、受験勉強を阻む症状をもたらしているのは、脳がどのような問題点を抱えているからなのか、正確にアプローチができます。
これは、志望校への合格を勝ち取る上で、生命線とも言える、とても大切なことです
急に勉強のヤル気がわかなくなった・・・、
イライラが収まらなくなった・・・、
問題が解けなくなった・・・、
これらは、受験ストレスの典型的な症状ですが、実は脳の中で起こっている異変はさまざまなのです。
たとえば、勉強へのヤル気がわいてこなくなくなったとしても、受験生のかた、お一人お一人、原因は異なります。
ある人は、脳内にあるA10神経の活動が低下して、ヤル気が出なくなる…。
別の人は、背外側前頭前野という脳の別の部分の問題で、ヤル気が出なくなる…。
原因が異なるわけですから、適切な対策も異なるのが当然です。
受験勉強の効率をアップさせるには、まず、脳機能の状態を浮き彫りにさせることが必要なのです。
光トポグラフィー検査は、まったく安全な検査です!
光トポグラフィー検査は、波長が800~2500μmの近赤外光(near infrared radiation)という光を頭に当てて、脳の活動状態を検出します。
この波長の光は、血液中のヘモグロビンに吸収される性質を持っています。
ですから、脳の大脳新皮質のそれぞれのエリアが、その瞬間、どの程度、活動して血液中の酸素を使っているのが、数値化できるわけです。
ぜひ、知っておいていただきたいのは、近赤外光(near infrared radiation)が人体にとってまったく安全であり副作用もないことは、医学的に完全に証明されているということです。


まず、ご紹介したい集中力アップの脳科学テクニックは、スマホやウェブカメラで、ご自分が勉強している姿を録画し続けることです。
なぜ、それで集中力が上るのか?
理由は、自分自身の勉強している姿を、カメラのレンズを通して第三者の視点で認知することができるからです。
これによって、脳内にあるメタ認知力という能力が高まり、自分自身の感情や脳の働きを客観的に点検や評価し、気づきを得ることができます。
脳科学では、こうした現象は「メタ認知モニタリング(Metacognitive Monitoring)」と呼ばれています。
さらに、メタ認知モニタリングによって自制心を高める脳内のスイッチがオンになります。
そのため、目標設定や計画、その修正といったメタ認知力の次の段階のプロセスが進むのです。
こちらは、脳科学では「メタ認知コントロール(Metacognitive Control )」といいます。
この2段階のプロセスが脳内で進行するため、自分の意思でより精神力を高めて勉強に取り組めるわけです。
実際、やってみるとわかりますが、ご自分が勉強している姿をウェブカメラやスマホで録画し続けると、それだけで、勉強の集中力が大幅に高まることは、ご自分でも実感できます。
受験生なら経験があると思いますが、塾や予備校の自習室では、自宅に比べると勉強の集中力がアップすることが多いものです。
そうなる理由は、誰しも、第三者に見られていることを意識すると、怠けたいといった欲望を理性の中枢である脳の前頭前野が自制するようになるからなのです。
だから、多くの受験生が勉強している自習室だと普通に勉強ができるのに、自宅で勉強しているときはダラケてしまうという悩みを抱えています。
その最大の原因が、第三者の視点がなくなってしまうことにあったのです。
それをおぎなうのが、カメラで自分の姿を録画することによって、擬似的に自習室と同じ脳の状態に変えるということなのです。
カメラで録画する場合は、自分が勉強している姿を見ることができるのは、未来の自分です。
つまり、現在の自分を監視するのは、未来の自分だということになります。
それでも、欲望を自制する心理は強力に働きます。
なぜなら、現在の自分はダラケている自分を許容しても、未来の自分に対しては、胸を張れる立派な自分でありたいと思う心理が働くからです。
といっても、勉強している姿を再生して見るのは時間の無駄です。
基本的には、録画しっぱなしで結構です。
ただし、午前、午後、夜など、まとまった勉強が終わったら、ところどころ、早送りで部分的に再生し、その日の勉強の集中力を5段階で採点しましょう。
平均が3点。
ものすごく集中できていたら最高得点の5点。
最悪は1点。
2点と4点は、その中間です。
このように自己採点をすると、脳内で「メタ認知モニタリング(Metacognitive Monitoring)」や「メタ認知コントロール(Metacognitive Control )」を遂行している前頭前野が強化されます。
だから、勉強を頑張るという意思がパワーアップしてくれるので、二重にメリットがあります。
とは言え、録画の再生や自己採点に時間をかけると本末転倒なので、1日3回、それぞれトータル3分以内で、ざっくりと評価するようにしましょう。
特に自己評価が1点や2点の日は、どうしようもなく自己嫌悪に陥ります。
しかし、その悔しさが、次の勉強の集中力を生み出す原動力になってくれます。
そのプロセスで脳の前頭前野も強化されるわけです。
ただし、受験ストレスが激しく、「受験うつ」に陥っている場合は、この方法を実践するのはかえって危険です。
ほんの少しでも抑うつ症状が出ている場合は、この方法は禁止です。
自己採点をして1点や2点をとってしまった場合、自己嫌悪によって抑うつ症状が悪化するからです。
まず、こちらで受験ストレスの状態をセルフチェックしていただき、該当するストレス項目がない場合に実践してください。
受験ストレスセルフチェック
⇒ クリック!
では、「受験うつ」の場合は、どうすれば前頭前野を活性化し、勉強の集中力を高められるのか?
その答えが、前頭前野に磁気のパルスを当てて、直接、刺激をすることなのです。
これによって「受験うつ」が治ると同時に、前頭前野の機能が高まるため、勉強の集中力もアップするわけです。
一般的には、治療以外に悪い影響が出ることだけが副作用と思っている方が多いようですが、この場合は、勉強の集中力が高まるという良い方向の副作用が出るわけです。
ぜひ、以下の磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コースについての紹介もお読みください。
【受験生の「コロナうつ」にも対応しています!】

✓ 受験勉強の集中力・記憶力・ヤル気の低下は、精神論で解決できません。
✓ 受験の脳機能に特化した専門の「磁気刺激治療」が合格への最短コースです!
✓ 勉強の方法を変えるだけで脳機能を高められるのが「受験に特化したCBT治療」です!
✓ 光トポグラフィー検査による脳の活動データを元に、必要に応じて以下の5つの特別診療も併用します!


もちろん、「学力」は高いに越したことはありません。
でも、いくら猛勉強したからといって、「学力」を高められる水準には限界もあるのも現実です。
だからこそ、受験生は志望校への合格をさらに確実に手にするために、「脳のスペック」を高めることにも努力をするべきです。
特に最近では、脳医学の発展で「脳のスペック」を高める方法が次々と解明されています。
具体的な方法は、①睡眠、②運動による脳への刺激、③飲食物による脳への刺激、④磁気による脳への刺激などです。
受験生の方に真っ先に見直してほしいのは、「①睡眠」についてです。
脳のスペックが最も高まる睡眠時間は、人類の平均を取ると7時間30分という数字が出ています。
でも、「だったら私も、7時間半、寝ればいいんだ!」と、早合点しないでください。
これは遺伝子によるバリエーションがとても大きいということがわかっています。
アインシュタインのように10時間の睡眠が必要な人もいます。
私の恩師でもあるのですが、ノーベル賞を受賞された小柴昌俊先生は11時間、睡眠を取られていました。
こういうタイプの人は、ロングスリーパー遺伝子を持っています。
逆に、ショートスリーパー遺伝子を持っていると、3時間の睡眠でも十分だというタイプの人もいます。
では、どうすれば、あなたの脳のスペックが最も高まる、最適な睡眠時間を知ることができるのでしょうか?
答えは簡単です。
実際にその睡眠時間を試してみればいいのです。
遺伝子検査なんて、しなくてけっこうなわけです。
ただし、睡眠時間の影響は、翌日だけではなく数日間は残ります。
だから、一晩だけで睡眠の効果を評価してはいけません。
ポイントは、3日間、連続して、同じ時間だけ眠ってみること。
たとえば、7時間半、7時間半、7時間半と3日連続で眠ってみるわけです。
その状態で過去問を解くなどして、脳のコンディションをチェックしてみましょう。
入試まで月日がある今の時期に、いろいろ試しておいて、このあたりがベストかなという時間を見つけておくといいです。
あとは入試の日程がすべて終わるまで、その睡眠時間にフィックスさせればいいわけです。
メンタル面のご病気もあったので、遺伝子だけの問題ではないのですが、私の心療内科クリニックでは、1日12時間眠ると脳のスペックが最大化することが判明した受験生もいました。
12時間も眠るのは、日中の時間管理がとっても大変です。
ですが彼は、しっかりと12時間の睡眠を1年間にわたって実践し、念願の医学部にみごと合格されました。
ぜひ、みなさんも、なんとしても志望校に合格したいという強い想いをもって、日中の中に潜んでいる無駄な時間を徹底的に排除し、最適な睡眠時間を維持してください。
次に、「②運動による脳への刺激」で脳のスペックを高める方法をご紹介しましょう。
色んな運動についての脳への効果が脳医学の研究で解明されていますが、私が数多くの論文を読んだ中で、おそらく効果が最強だと考えられるのは、「運動認知デュアルタスク」と呼ばれるものです。
デュアルタスクとは、異なる2つの作業を同時に行うということです。
デュアルが2つ、タスクが作業という意味です。
何でも異なることを同時にやれば、すべてデュアルタスクなのですが、その中でも、片方が運動、もう片方が頭をつかう認知作業という組み合わせが「運動認知デュアルタスク」です。
脳内で運動と認知という二つの異なる方向から同時に脳が刺激されることで、脳の発達を強力に促す作用を持っているのです。
たとえば、机の前で屈伸運動をしながら数学の計算問題を解くと、とても質の良い「運動認知デュアルタスク」となります。
あるいは、やはり机の前で屈伸運動をしながら、英単語や歴史の暗記物をこなすということでも、「運動認知デュアルタスク」となります。
ぜひ、こちらも実践っしてみてください。
「運動認知デュアルタスク」について、詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
NASAが行う頭が良くなる訓練は自宅で誰でもできる【受験の脳科学】
https://ameblo.jp/yoshida-takayoshi/entry-11902644678.html
ただし、脳のスペックを高める効果の強さとしては、格段に大きいのが④磁気の脳への刺激です。
特に受験ストレスなどでスペックの低下を起こしている脳については、大きな効果を発揮し、志望校への合格に役立っています。
私のクリニックでは、このことにフォーカスし、磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コースという専門のプログラムを設けています。
実際、今年の入試についても、多くの受験生が偏差値のランクでいうと2ランクぐらいレベルの高い大学に合格を勝ち取っています。
ぜひ、以下の説明もご一読ください。
【受験生の「コロナうつ」にも対応しています!】

✓ 受験勉強の集中力・記憶力・ヤル気の低下は、受験うつや受験ストレスによる脳機能の不調によって生じる場合が多いのが特徴です。
✓ 受験に特化した専門の「磁気刺激治療」は、脳機能の不調を根本的に治療することにより、受験うつや受験ストレスに起因する障害を取り除き、志望校への合格に必要な集中力・記憶力・ヤル気の回復を図ります。
✓ 脳機能に合致した勉強方法への改善など「受験に特化したCBT治療」を組み合わせることにより、磁気刺激治療の効果を志望校へに合格に直結させられます!
✓ 光トポグラフィー検査による脳の活動データを元に、必要に応じて以下の5つの特別診療も併用します!
✓ メンタル医学と脳科学を応用した以上の診療を組み合わせ、志望校への合格を実現しましょう!
集中力・記憶力・思考力・勉強のヤル気・イライラ・・・。
これらは、脳内のニューロン(神経細胞)によるネットワークが生み出す現象です。
「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」は、ここに着目し、以下の3つの専門的な治療法を組み合わせることにより、志望校への合格を図ります。
① 受験の脳機能に特化した専門の「磁気刺激治療」
② 受験勉強の方法を変えることにより脳機能を高める「CBT治療」
③ 光トポグラフィー検査のデータを元に、脳機能そのものを高める5つの特別診療
つまり、
「受験専門・磁気刺激治療」+「受験に特化したCBT治療」+「5つの特別診療」=志望校への合格
これが弊院で提唱している「合格の方程式」です!
「磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コース」は、短期間でも効果が出やすいという特徴があります。
志望校への合格をあきらめないでください!
磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コースの大きな柱の一つが「受験に特化した磁気刺激治療」です。
磁気刺激治療とは、頭の外から脳に磁気のパルスを当て、うつ病を治療する先進医療です。
早期に治療効果が現れるのが最大の特徴で、目立った副作用は、ほとんどありません。
米国では高い治療実績があがっており、画期的な最新治療として全米各地で急速に普及しています。
ただし、大うつ病性障害や双極性障害といった一般的なうつ症状には、既存の磁気刺激治療でも一定の治療効果が見込めるものの、受験生が合格を勝ち取るには、そのために特化した脳機能の改善が不可欠です。
実際、既存の磁気刺激治療を受けた受験生が、
・うつ症状は治ったものの試験の得点力は上がらず、結局、不合格になって、うつ病が再発した・・・。
・そもそも模擬テストの点数も上がらないので、そのストレスで、ちっとも治らない・・・。
こうしたケースが多く見られます。
そこで弊院では、まず、以下の検査を行い、それに合致した磁気刺激治療を行っています。
・勉強中の脳の活動を測定し、なぜヤル気が起きないのか、なぜ記憶できないのか、問題点を画面に可視化する。
・模擬テストの解答と光トポグラフィー検査のデータを脳科学とメンタル医学で分析し、得点アップのために必要な脳の改善点を究明する。
・試験を解いている最中の集中力を1ミリ秒(千分の1秒)単位で測定し、得点アップの鍵を握る脳のエリアを特定する。
以上の分析結果をもとに、一般的な磁気刺激治療ではできなかった、志望校への合格を勝ち取る治療へと進化を図るのことができました。
これが、「受験に特化した磁気刺激治療」なのです。
「受験に特化した磁気刺激治療」と並び、磁気刺激治療(受験うつ)早期合格コースの基本となる柱が、「受験勉強のCBT治療」です。・・・