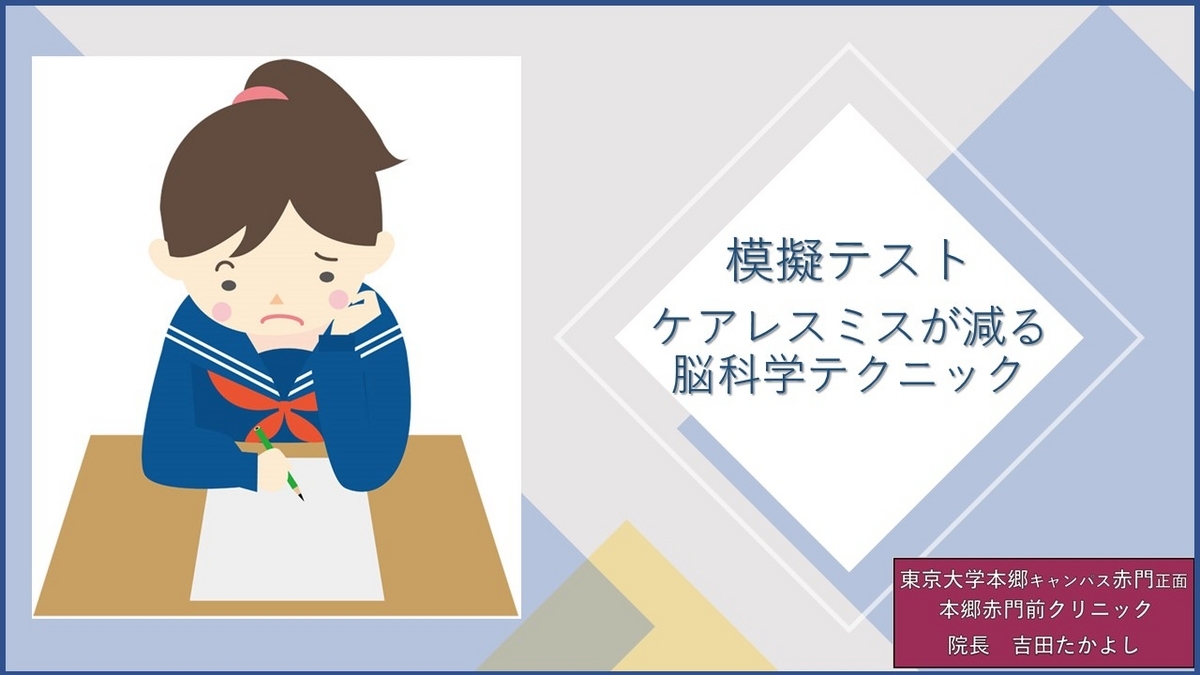

ケアレスミスの対策は、飛行機事故の分析で発展!
ケアレスミスを防ぐための研究が最も進んだのは、飛行機事故の分析です。
入学試験や定期テストのケアレスミスも困りますが、飛行機の操縦や整備のケアレスミスの場合は事故に直結し、人の命が失われます。
だから、世界各国で研究予算が投入され、ケアレスミスの削減方法が発達したのです。
その研究成果は、病院での医療事故の対策にも用いられています。
私自身も、医者になりたての頃に研修を受けた経験があります。
精神力に頼らない方法で、科学的にケアレスミスを未然に防ぐ効果の大きさを実感させられました。
この理論を受験生の実態にあわせて方法論に落とし込めば、試験のケアレスミスの削減にも有力な手段となるわけです。
模試の自己採点のときに科学の目でケアレスミスを検証!
受験生は、模擬テストなど試験を受けたあとに、自己採点をしますよね。
もちろん、そのときに、ケアレスミスのチェックもしていただきたいのですが、ただ、「ケアレスミスをしちゃった!残念!」ですませてしまってはいけません。
次回、テストを受けたときに、その残念なケアレスミスを繰り返さないためには、脳科学に基づく適切なチェックポイントで検証する必要があるのです。
チェックポイントは10種類ほどありますが、その中で、誰でも簡単にチェックできるポイントを、一つ、ご紹介しておきましょう。
それは、テストの開始5分以内と、最後の5分にケアレスミスが起きやすいということです。
試験の開始直後5分間はケアレスミスを誘発する魔の時間帯!
開始直後は、脳がまだ、問題を解くということに慣れていないため、ケアレスミスが生じます。
スポーツの試合なら、体が十分に温まっていなくてミスをするといいますが、模擬テストも、いわば、脳が温まっていなくてミスするわけです。
つまり、試験の開始直後5分間は、「ケアレスミスを誘発する魔の時間帯」だというわけです。
ただし、試験開始直後のケアレスミスについては、個人差がとても大きいことが分かっています。
だから、模試が終わったら、必ず、ご自身にこうした傾向がないかをチェックしましょう。
そして、危険性が高いと判断したら、その受験生については、はじめの5分間だけ、少しスローペースで、つまり安全運転で問題を解くべきだということです。
脳の環境への適応能力で「魔の5分間」のケアレスミスが決まる!
脳医学の研究でわかってきた大事なポイントは、受験生全員が、開始直後の5分間にスローペースの安全運転で問題を解くべきだというわけではないということです。
人間の脳には、どれだけ新しい環境に適応しやすいか、脳の性質に個人差があります。
さらに、環境への適応力は、対人関係に反映されることも、メンタル医学の研究で解明されています。
結論だけ簡単にご紹介すると、新しい環境に適応する能力が低い人は、対人関係が苦手でストレスを感じやすい傾向があるのです。
人付き合いは、刻々と変わる話題や、相手の感情といった、いわば新しい環境に適応する連続なので、こういう研究結果がでることは、心療内科医として大いに頷けます。
大事なのは、こういうタイプの人が、初めの5分間にケアレスミスが出やすいということです。
逆に、対人関係が得意でストレスも感じにくい人は、無意識のうちに新しい環境に適応するのが得意なので、最初の5分間に特にケアレスミスが出るという傾向は出にくくなります。
5分間とはいえ、スローペースで問題を解くというのは、制限時間と勝負しなければいけない入試では、わずかとはいえ時間を損してしまいます。
自分のタイプをよく見極め、これまで受けた試験の結果も分析し、時間を損する以上のメリットがある人のみ、冒頭の5分間をスローペースで解くようにしましょう。
試験終了の直前の5分間は、ケアレスミスが起きる第2の魔の時間帯!
一方、試験終了前の5分は、慌ててしまうため、やはりケアレスミスが生じやすくなります。
こうしたミスをした経験のある人は、終了直前に「やっぱり、コッチのほうが正しそうだ・・・」などと、直感に頼って解答を変えるということは、やるべきではありません。
ただし、こちらについても個人差がありますので、解答を変えた方が有利になる人も少なくないのです。
試験終了前の5分間にケアレスミスをしやすいかどうかは、メンタル面のストレス耐性のキャパシティで決まります。
個人差が大きいということについては、試験開始直後の5分間と同じなのですが、格差をもたらす脳科学的な因子は全く異なるというのが、とても興味深いところです。
大事なのは、試験開始直後と試験終了直前のそれぞれについて、ご自分の傾向を知った上で、自分の脳の性質にぴったり合ったケアレスミス対策の方法を、できるだけ早く確立しておくということです。
試験のケアレスミスの半分はストレス耐性の限界がもたらす!
こうした試験開始直後と終了直前のケアレスミスについては、誰でも簡単にチェックできますが、それ以外のケアレスミスも脳医学に基づく何らかのロジックで生じます
特に、ストレス耐性の限界によって生み出されるケアレスミスは、とても多く、これだけで模擬テストのケアレスミスの半分ほどを占めます。
このように、試験の答案用紙を脳医学の面から分析することは、志望校への合格を勝ち取る上でとても有益です。
そこで、受験生の方には模擬テストの答案用紙を持ってきてもらって、私が脳科学とメンタル医学に基づいて、分析することにしています。
ぜひ、以下の解説もお読みください。
Assessment of Examination Scripts

✓ 模擬テストの答案用紙を最新の脳医学やメンタル医学の知見を用いて科学的に分析すると、受験生の脳が試験の最中にどのように働いているのか把握でき、それに合わせて対策を取ることで受験生の脳が持つ潜在能力を最大限に引き出すことが可能となります。
✓ ①答案の構成における異常、②文章における不自然な記述形式、③文字に現れる脳機能の状態など、5つの項目について模擬テストの答案用紙を脳医学の観点から分析をすると、試験を受けているときに受験生の脳がどのように働いているのか科学的に把握できます。
✓ 模擬テストでケアレスミスがどのような脳の機能の問題で生じたのかを分析し、脳のストレス耐性の限界など要因を明確化して予防策を実践すると、それだけで平均して70%のケアレスミスを削減することが可能です。
✓ 自宅で勉強しているときと、会場で試験を受けているときでは、脳内にある扁桃体や前頭前野を中心に脳の働き方が根本から異なっており、これに対する対策が不十分だと、学力は高いのに入試に落ちるという悲劇が起きます。
✓ 答案用紙を解析して得られた5つの項目のデータをもとに、AmosやSPSSといった解析ツールを用い、試験に特化した光トポグラフィー検査のデータと組み合わせて共分散構造分析にかければ、脳のそれぞれの機能を改善させる方法が浮き彫りになります。
模擬テストの答案用紙は、試験中の受験生の脳機能を診断する上で、宝の山だと言えます。
受験うつ・受験パニック・受験不眠・受験恐怖症・・・。
これらは、受験生に急増しているご病気ですが、こうした症状は例外なく模擬テストの答案用紙に現れます。
脳機能に何らかのトラブルを抱えると、単に成績が悪くなるだけでなく、回答の仕方にも、独特なクセが現れます。
それを丁寧に読み取っていくことで、受験生の脳機能に何が起こっているのかが分析できるのです。
これは、志望校への合格を勝ち取るために、脳のどの部分の問題を解決すべきなのか、どの脳機能を改善すべきなのか、とても役立つ情報を教えてくれます。
受験生の脳機能が試験の最中に、どのように働いているのか、直接計測できれば、合格を勝ち取る上で決定的に有利になります。
実際、これについては開発が進んでいます。
当院の院長が理事を務める人間情報学会では、受験生が試験を受けている真っ最中でも、生体情報を計測し続けることができる超小型の装置の開発に成功しました。



